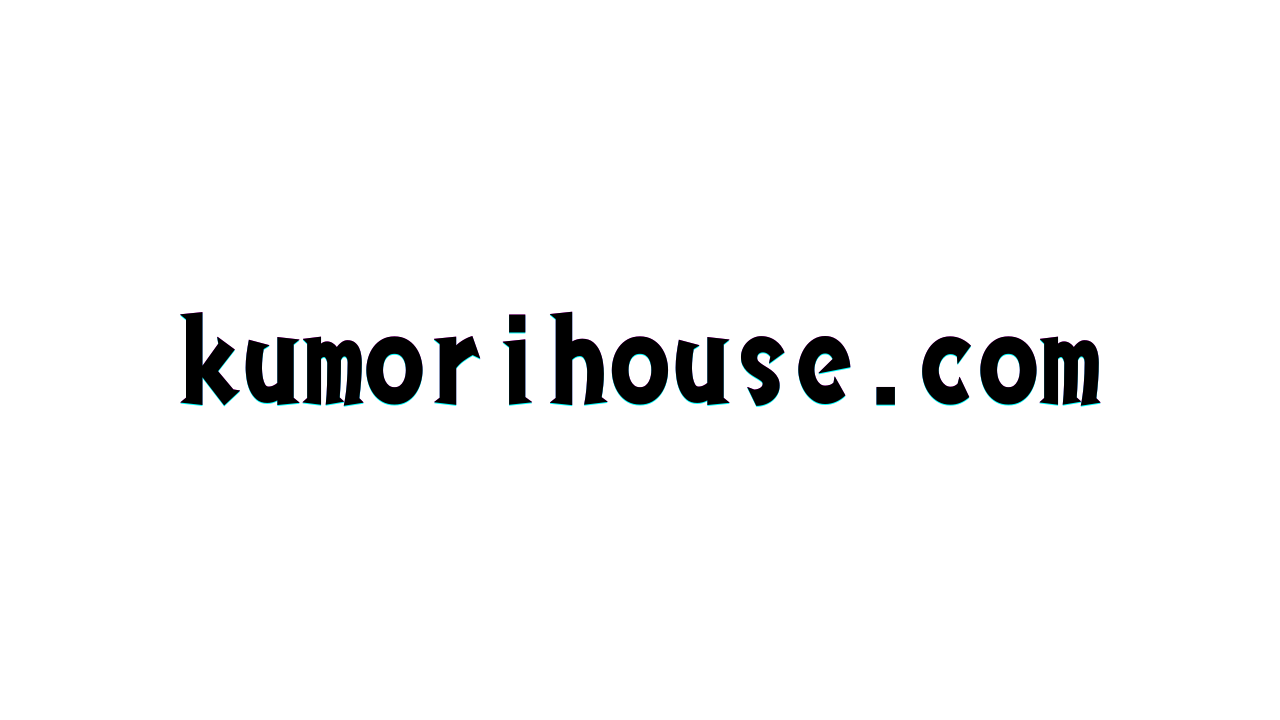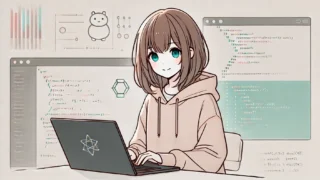こんにちは!kumoriのお部屋へようこそ。
プログラミングを学んでいると、「演算子」という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
演算子は、数値や変数を操作し、計算や比較を行うための重要な存在です。
今回は、演算子の基本や種類、Pythonでの使い方を初心者向けに分かりやすく解説します!
それではいきましょう!
プログラミング学習のロードマップはこちら!
演算子とは、「計算」するための記号
「演算子」とは、数値やデータを使って計算や比較をするための記号のことです。
次のような計算を考えてみましょう。
x = 10 + 5
print(x)
実行結果
15
今回用いた +(プラス記号)は「加算演算子」と呼び、2つの数値を足し算するための演算子です。
演算子には、計算以外にも、値を比較したり条件を組み合わせたりするものもあります。
次の章では、Pythonで使われる主な演算子と、その使い方を詳しく紹介していきます!
演算子の種類と使い方
Pythonにはさまざまな演算子がありますが、
今回は特に重要な「算術演算子」「比較演算子」「論理演算子」の3つを紹介します。
1. 算術演算子(数値の計算を行う)
算術演算子は、数値の計算を行う演算子です。
Pythonの算術演算子には、以下の種類があります。
| 演算子 | 名前(正式名称) | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
+ | 加算演算子 | 5 + 3 → 8 | 2つの数値を足し算する |
- | 減算演算子 | 5 - 3 → 2 | 2つの数値を引き算する |
* | 乗算演算子 | 5 * 3 → 15 | 2つの数値を掛け算する |
/ | 除算演算子 | 5 / 2 → 2.5 | 割り算を行い、結果は 小数(float)になる |
// | 整数除算演算子 | 5 // 2 → 2 | 割り算の結果の 小数点以下を切り捨て |
% | 剰余演算子 | 5 % 2 → 1 | 割り算の余り(剰余)を求める |
** | 累乗演算子 | 2 ** 3 → 8 | 指数計算 (2の3乗 = 2 × 2 × 2) |
使い方
それぞれの演算子がどのように動作するのか、実際にPythonコードで確認してみましょう!
a = 10
b = 3
print(“加算:”, a + b)
print(“減算:”, a – b)
print(“乗算:”, a * b)
print(“除算:”, a / b)
print(“整数除算:”, a // b)
print(“剰余:”, a % b)
print(“累乗:”, 2 ** 3)
実行結果
加算: 13
減算: 7
乗算: 30
除算: 3.333…
整数除算: 3
剰余: 1
累乗: 8
算術演算子はプログラミングの基本ですが、実際のコードでは単独で使うことは少なく、条件分岐やループ処理と組み合わせて使うことが多いです。
%(剰余演算子)を使って偶数・奇数を判定したり、//(整数除算)を使ってページネーションを作成したりすることもできます。
ページネーションとは
大量のデータを複数のページに分割して表示する仕組みのことです。
2. 比較演算子(値を比較する)
比較演算子は、2つの値を比較し、結果を True(真)または False(偽)として返す演算子です。
「AのスコアはBより高いか?」「年齢は18歳以上か?」など、条件を判定するときに役立ちます。
Pythonの比較演算子には、以下の種類があります。
| 演算子 | 名前(正式名称) | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
== | 等価演算子 | 5 == 3 → False | 左右の値が等しいか を判定 |
!= | 不等価演算子 | 5 != 3 → True | 左右の値が異なるかを 判定 |
> | 大なり演算子 | 5 > 3 → True | 左の値が右より大きいかを判定 |
< | 小なり演算子 | 5 < 3 → False | 左の値が右より小さいかを判定 |
>= | 大なりイコール演算子 | 5 >= 5 → True | 左の値が右以上か を判定 |
<= | 小なりイコール演算子 | 5 <= 3 → False | 左の値が右以下か を判定 |
比較演算子の使い方
x = 10
y = 5
print(“等しいか:”, x == y)
print(“異なるか:”, x != y)
print(“大なり:”, x > y)
print(“小なり:”, x < y)
print(“大なりイコール:”, x >= y)
print(“小なりイコール:”, x <= y)
実行結果
等しいか: False
異なるか: True
大なり: True
小なり: False
大なりイコール: True
小なりイコール: False
比較演算子は、プログラムが「条件を判断する」ために欠かせない要素です。
スピード違反のチェック、ポイント特典の判定、ログイン認証など、日常生活のさまざまな場面で使われるロジックも、比較演算子があれば実装できます。
論理演算子(複数の条件を組み合わせる)
論理演算子は、複数の条件を組み合わせて、より複雑な判断を行うための演算子です。
「80点以上かつ欠席が3回以下なら合格」「AかBのどちらかが当てはまればOK」といった条件を表現できます。
論理演算子の種類
Pythonには、次の3つの論理演算子があります。
| 演算子 | 名前(正式名称) | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|
and | 論理積(AND) | (x > 5) and (y < 10) | 「両方の条件が True 」なら True、「どちらかが False」なら False |
or | 論理和(OR) | (x > 5) or (y < 10) | 「どちらか一方でも True」 なら True |
not | 論理否定(NOT) | not(x > 5) | True を False に、False を True に反転 |
論理演算子の使い方
x = 8
y = 3
print(“AND:”, (x > 5) and (y < 10))
print(“OR:”, (x > 5) or (y > 10))
print(“NOT:”, not(x > 5))
実行結果
AND: True
OR: True
NOT: False
コードの解説
AND
x = 8
y = 3
print(“AND:”, (x > 5) and (y < 10))
- x > 5
- x には 8 が入っているので、「8 は 5 より大きいか?」を判定。
- 8 は 5 より大きいので、これは「正しい」(True)。
- y < 10
- y には 3 が入っているので、「3 は 10 より小さいか?」を判定。
- 3 は 10 より小さいので、これも「正しい」(True)。
- 結果
- and は、両方の条件が正しい場合にだけ「正しい」と判定する。
- 今回はどちらも「正しい」ので、結果は True になる。
OR
x = 8
y = 3
print(“OR:”, (x > 5) or (y > 10))
- x > 5
- x は 8 なので、「8 は 5 より大きいか?」を判定。
- 8 は 5 より大きいので、これは「正しい」(True)。
- y > 10
- y は 3 なので、「3 は 10 より大きいか?」を判定。
- 3 は 10 より大きくないので、これは「正しくない」(False)。
- 結果
- or は、どちらか一方でも「正しい」なら、全体の結果を「正しい」とする。
- 今回、1つ目の条件が「正しい」ので、結果は True になる。
NOT
x = 8
y = 3
print(“NOT:”, not(x > 5))
- x > 5
- x は 8 なので、「8 は 5 より大きいか?」を判定。
- 8 は 5 より大きいので、これは「正しい」(True)。
- 結果
- not は、判定結果を反転する(「正しい」→「正しくない」)。
- 今回は True を not で反転するので、結果は False になる。
演算子の優先順位
① 算術演算子の優先順位
算術演算子は 数学の計算と同じルール で処理されます。
優先順位が高い順
| 優先度 | 演算子 |
|---|---|
| 1位 | ()(カッコ) |
| 2位 | **(累乗) |
| 3位 | * / // %(掛け算・割り算) |
| 4位 | + -(足し算・引き算) |
コード例
print(2 + 3 * 4) #掛け算が先に計算される
print((2 + 3) * 4) #カッコの中が先に計算される
print(2 ** 3 + 1) #累乗が先に計算される
実行結果
14
20
9
② 比較演算子の優先順位
比較演算子は、左から順に優先されます。
コード例
print(10 > 5 == True) # `10 > 5` が先に計算される
実行結果
True
③ 論理演算子の優先順位
論理演算子では、「not」が最優先となります。
| 優先順位 | 演算子 |
|---|---|
| 1位 | not(否定) |
| 2位 | and(かつ) |
| 3位 | or(または) |
notが最優先
print(not True and False)
処理の流れ
- not True を計算 → False
- False and False を計算 → False
実行結果
False
カッコを使うと順番が変わる
print(not (True and False))
処理の流れ
- True and False を計算 → False
- not False を計算 → True
実行結果
True
些細な違いで結果は大きく変わるので、正しい理解が必要です。
Pythonには他にも「代入演算子」や「メンバーシップ演算子」など、特定の用途で便利な演算子もあります。
しかし、そうした演算子はプログラムを書いていくうちに自然と学ぶ機会があるため、
まずは今回紹介した3つの演算子をしっかり理解し、実際に使いながら慣れていきましょう。
次に学ぶべき記事を紹介
計算結果によって処理を分岐させる方法を学ぶために、「条件分岐」を理解しましょう!
最後に
ここまでブログを読んでいただき、ありがとうございました。
演算子を使いこなせると、計算や条件分岐を自由に操れるようになり、プログラムの幅がぐっと広がります。
ぜひ実際にコードを書きながら、演算子の便利さを楽しんでみてください!